私達世代だとお嫁入り道具の一つに、着物を持たされた方は多いかと思います。
私も例に漏れず、黒留袖から喪服まで一式持たされました。
誤解のないように最初にお伝えすると、それはとてもありがたいことで文句を言おうなんてこれっぽっちも、、、いやほんの少しだけ、、、いらなかったかも。
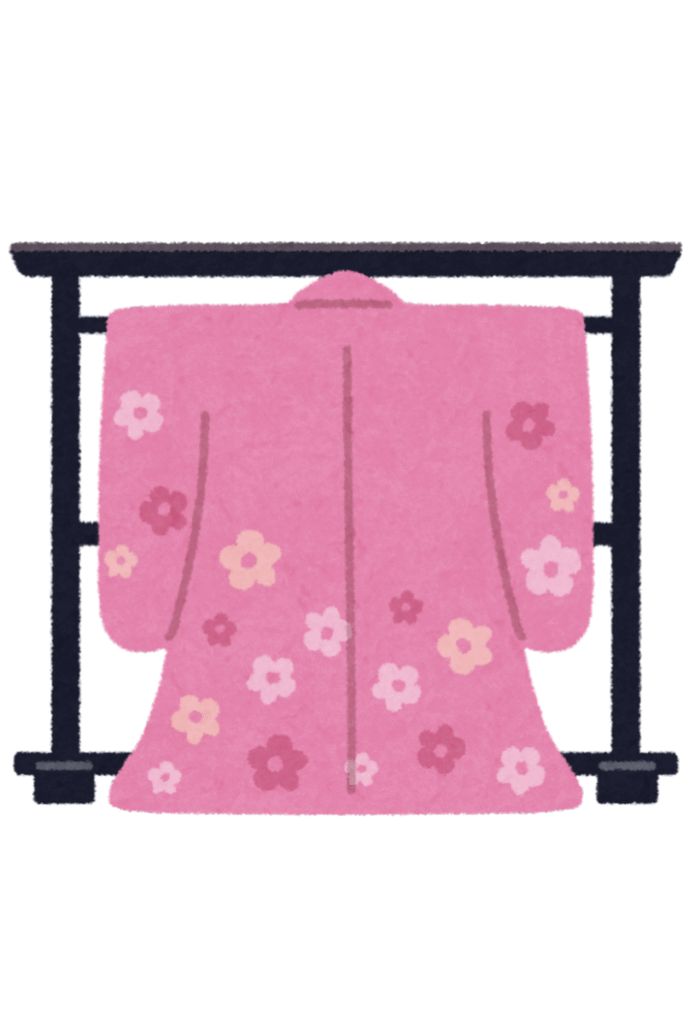
時は令和、この着物たちはどうしたら良いのやら、、、。
曾祖母、祖母や母が着物を着る生活に触れて生活をしていた明治、大正、昭和初期ならきっと大活躍していたことでしょう。

でも昭和の核家族で育った私は幼い頃から着物に触れる生活などほぼなく、母が小学校の入学式で着ていたかも、、、というおぼろげな記憶しかありません。
そんな私が結婚したときに大量の着物とそれを収納する桐たんすを持たされたわけです。
どうしろと!?
長子が生まれ、初節句、七五三、その子が小学校入学する時にも頑張って着物を着ました。
そりゃ端から見たらね、着物を着こなしている母親はとっても素敵だし心から憧れます。
でもね、着付けがね、大変すぎる。大変すぎるのよ。手がつります(涙)。
それに兄弟が生まれたらそれどころじゃないんですよね。

着物を着たら赤子のよだれで着物を汚されないように神経を使うし、雨が降ろうものなら仮病でも使おうかという気分にもなります(私だけ?)
昔の人達はどうしていたのでしょうか、、、。
そんなこんなで段々と着物から遠ざかり、着物は結婚後2,3回着て桐たんすに封印。そのあとは桐たんすを開けることもなくなりました。
桐たんすを見る度に、こんなに高価なものを持たせてもらったのに活用できなかった母への懺悔の気持ちが拭えませんでした。
そんな私に転機が訪れたのは半年前。近所に住む友人が着付け教室に誘ってくれたのです。
話を聞くと、彼女も母親やお姉さんの着物がたくさん回ってきて、それを機会に着物生活をしてみようと思ったようでした。
私自身、子育ても終りが見え始め第二の人生をどう過ごすかを模索していた時期だったので喜んでお誘いを受けました。
するとどうでしょう。あんなに苦手に思っていた着付けが楽しい!
着物に触れていると、時を忘れて着物と帯の組み合わせを考えている自分がいました。
布の織り方や材質によってランク分けされ、どんなシュチュエーションでどの着物がマッチするか?そんなことを考えているのが楽しくなりました。
どんな思いでこの着物が作られたのか、その地域だからこそ生まれた技術、そんなことを知れば知るほど着物の奥深さに魅了されていきます。


自分でも自分の変化に驚いています。嫁入り道具として持たせてくれた母への感謝の気持で’ありがとう’と心の中で手を合わせています(母はまだ健在です笑)。
今はもう、嫁入り道具に着物を、、、なんてことは少なくなっているのでしょうね。
メンテナンスを考えると、もはや贅沢品以外の何物でもない気もします。
それでも、もし皆さんのご自宅に眠っている着物があったらぜひ広げて見てあげてほしいと思います。
見ているだけでも素敵な発見がたくさんあります。
そしてもし機会があればそれを着てお出かけしてみてはどうでしょう?
子育て中にはとても考えられなかった楽しみが、これから見つけられるかも知れません。



コメント